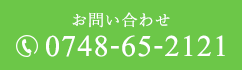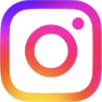胃炎とは
胃炎とは、胃の粘膜に炎症が起きた状態です。
ピロリ菌感染が原因の場合、放置すると胃・十二指腸潰瘍や胃がんのリスクが高まります。
胃炎の診断は、病理検査で胃粘膜の炎症を確認することで確定されます。
胃のむかつきや重だるさなどの自覚症状は「症候性胃炎」と呼ばれます。
かつては、胃の症状があれば「胃炎」と診断されていましたが、現在ではピロリ菌感染による胃炎と、機能性ディスペプシアなどの機能低下による胃の症状は区別されています。
急性胃炎と慢性胃炎の違い
胃炎には、食べ過ぎ、飲み過ぎ、過度のストレス、喫煙などが原因となる急性胃炎と、ピロリ菌感染などが原因となる慢性胃炎があります。
急性胃炎
急性胃炎は短期間で急激に発症し、原因が特定しやすいため、比較的早く治療が完了することが多いです。
症状チェック
- 胃やみぞおちの痛み
- 胸やけ
- むかつき
- 吐き気
- 嘔吐
- 腹部膨満感や不快感
- 吐血・下血
原因
ストレスや薬の副作用、唐辛子などの刺激物や、食べ過ぎ・飲み過ぎが主な原因です。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)
急性胃炎とは異なり、慢性胃炎は症状が長引きます。
治療に時間を要すことも多く、原因も複雑です。
症状チェック
- 食前の胸やけ
- 食後のむかつきや胃もたれ
- 胃やみぞおちの痛み
- 食欲不振
原因
当院の患者さんにおいては、ピロリ菌感染が慢性胃炎の主な原因です。
再発を防ぐには、除菌治療によるピロリ菌の除去が効果的です。
胃炎の種類
びらん性胃炎
びらん性胃炎は、胃粘膜がただれた状態で、急性と慢性があります。
主な原因は、アルコールの過剰摂取、ストレス、非ステロイド系抗炎症薬やアスピリンの使用、クローン病、細菌やウイルス感染などが挙げられます。
非びらん性胃炎
非びらん性胃炎は、胃粘膜に明らかなびらん(ただれ)を認めないものの、慢性的な炎症が生じている状態です。
胃の内視鏡検査では粘膜の発赤や浮腫などが見られることがありますが、組織学的には炎症細胞の浸潤などが確認されます。
主な原因としては、ヘリコバクター・ピロリ菌(H. pylori)感染が最も多く、その他、自己免疫性胃炎や慢性的なストレス、薬剤(NSAIDsなど)も関与することがあります。
感染性胃炎
免疫機能が低下している方は、ウイルス性胃炎や真菌性胃炎を発症しやすくなります。
これは、がん治療や慢性の全身疾患、エイズなどで免疫抑制剤を服用している方などに当てはまります。
急性ストレス性胃炎
びらん性胃炎の一種である急性ストレス性胃炎は、胃酸分泌量の増加や胃粘膜のバリア機能の低下、血流の低下などによって引き起こされます。
代表的な原因は、広範囲の火傷、頭部の怪我、大量出血を伴う怪我などの身体的ストレスです。
放射線性胃炎
放射線性胃炎は、胸部左下、上腹部への放射線照射によって胃粘膜に炎症が起きることで発症します。
萎縮性胃炎
当院の患者さんにおいては、ピロリ菌感染を主な原因として、胃の運動機能が阻害されることがあります。
これは、胃粘膜の炎症により、胃酸や胃液を分泌する粘膜細胞の萎縮・収縮が起こっている状態で、無症状で進行することが特徴です
注意!萎縮性胃炎は胃がんに進行します
長期化した慢性胃炎は、胃粘膜が萎縮し萎縮性胃炎へと進行します。
さらに進行すると、胃粘膜が大腸や小腸の粘膜に似た状態になる腸上皮化生が起こります。
この腸上皮化生の一部ががん化し、胃がんを発症する可能性があります。
そのため、萎縮性胃炎は前がん病変と捉えられ、胃がん予防のため、当院では慢性胃炎の早期発見・早期治療を重要視しています。
胃炎の検査方法
当院では、まず問診で患者さんの症状、摂取した飲食物、服用中のお薬などについて詳しくお伺いします。
慢性胃炎の疑いがある場合は、胃カメラ検査(内視鏡検査)を実施し、胃粘膜の状態を観察します。
胃粘膜の萎縮は胃がん発症の可能性があるため、早期発見・早期治療のため精密な検査が重要です。
当院では、日本消化器内視鏡学会専門医による精密な胃カメラ検査で的確な診断と適切な治療を提供しています。
胃炎の治し方
急性胃炎の治療方法
急性胃炎の原因がピロリ菌や内服薬の場合は、内服薬の中止・変更、服用量の調整、除菌治療などを行います。
また、胃を休ませるため、食事内容の見直しや絶食、水分摂取を行うこともあります。
治療中は、コーヒー(カフェイン)、アルコール、香辛料など、胃粘膜を刺激したり、胃酸分泌を促進するものを避けてください。
慢性胃炎の治療方法
当院では、ピロリ菌が原因の場合は除菌治療を行います。
また、胃酸分泌抑制薬や胃機能改善薬も使用します。
慢性胃炎においても、胃粘膜への刺激を避ける食事や生活習慣の改善が重要です。